-
集客に強いホームページ
-
グラフィックデザイン
グラフィックデザイン -
LINE社認定パートナー事業
-
その他サービス
その他サービス -
会社案内
-
採用・パートナー募集
059-355-3939
受付時間/平日 9:00〜18:00
(土・日・祝を除く)

中国で勢いのあるSNSとして挙げられるのが、小紅書(RED)と呼ばれるアプリです。
画像や動画の投稿がメインとなっており、コスメやファッションなどの流行にも影響を与えています。
インバウンド集客に効果的として、日本企業の活用も増えており、小紅書の注目度は高まるばかりです。
しかし、小紅書の利用は危険をともなうと言われることもあり、「不安で運用するには至っていない」という方もいるでしょう。
この記事では、小紅書が「危険」と言われる理由について、安全に利用する方法を踏まえながら解説します。
弊社が実際に支援した運用事例もあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
小紅書(RED)とは

小紅書(RED)とは、主に中国で利用されているSNSのことです。
EC機能も備えられており、写真の投稿やコメント・レビューなど、Instagramと近い使用感になっています。
ユーザーは女性が7〜8割近くを占めており、30代以下の若い世代が中心です。
ライブ配信から商品の購入に進める点も、特徴として挙げられます。
中国人の女性や若年層をターゲットに集客したい場合には、小紅書の運用が特に効果を発揮するといえるでしょう。
小紅書の詳細や企業における活用方法について知りたい方は、下記の記事もぜひ一度チェックしてください。
【関連記事】小紅書(RED/レッド)とはどんなアプリ?日本企業における活用アイデアも解説
企業が小紅書(RED)を活用する際に注意すべきリスクとは?
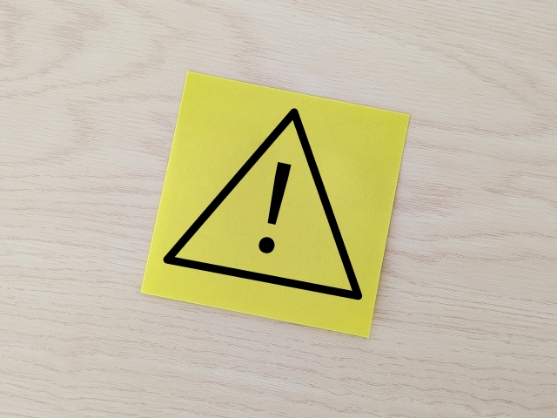
小紅書(RED)は中国・台湾を中心に高い影響力を持つSNSであり、訪日インバウンド集客でも活用の動きが進んでいます。
一方で、企業として小紅書を運用する場合には、事前に把握しておくべきリスクや注意点も存在します。
ここでは企業がREDを活用する際に押さえておきたい主なリスクとして、以下の3点を解説します。
- データプライバシーに関する配慮が必要
- 投稿の信頼性に関する社会的な目線
- 規約違反によるアカウント停止リスク
それぞれ詳しく見ていきましょう。
なお、弊社では、中国マーケティングの支援経験をもとに、リスクに配慮したRED運用をご提案しております。
RED運用担当者の採用も強化しており、興味のある方はぜひご連絡ください。
注意点①: データプライバシーに関する配慮が必要
REDを含む中国のSNSプラットフォームは、中国のサイバーセキュリティ法やデータセキュリティ法に基づき、国内サーバーへのデータ保存が義務付けられています。
そのため、企業としてREDを活用する際は、取り扱うユーザーデータやアクセスデータの管理に一定の注意が必要です。
自社のマーケティングデータやユーザー行動データの扱いに敏感な業種(例:医療、不動産、高価格帯商材など)は、特に情報管理体制の見直しが求められます。
注意点②: 投稿の信頼性に関する社会的な目線
REDでは、過去にフェイクレビューや誇張されたPR投稿が問題となり、2019年には一時的にアプリストアから削除された事例もあります。
このような背景から、現在は投稿内容に対するチェック体制が強化されており、企業としての投稿も「ステマ」や「虚偽表示」などがないよう厳密な配慮が求められます。
特に日本企業がREDでインフルエンサー(KOL)と連携する際には、投稿内容の監修体制やクリエイティブ表現の透明性を重視することが重要です。
注意点③: 規約違反によるアカウント停止リスク
REDの運用ガイドラインでは、利用規約違反に対する厳格な対応が明記されています。
不適切な広告表現、第三者の権利侵害、政治的・倫理的にセンシティブな内容を含む投稿は、アカウント停止・凍結・法的責任の追及などのリスクにつながります。
特に、日本企業にとって課題となりやすいのが「現地ルールとのギャップ」や「言語の壁」です。
そのため、小紅書を安全かつ効果的に運用するには、現地事情に精通したパートナーと連携することが推奨されます。
企業が小紅書(RED)を安全にビジネス活用するための方法

小紅書(RED)は、台湾や中国本土をはじめとする中華圏向けのマーケティング手法として注目されていますが、海外SNSならではの注意点も存在します。
企業としてREDを活用する際は、意図しない規約違反や炎上リスクを避けるためにも、正しい運用体制を整えることが重要です。
ここでは、企業がREDを安全にビジネス活用するための2つのポイントを解説します。
- 中国独自のガイドラインに反する投稿を回避する
- REDに精通したパートナーと連携する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ポイント①:中国独自のガイドラインに反する投稿を回避する
企業アカウントであっても、REDの利用には明確なルールが存在します。
特に以下のような内容は、投稿が削除されたり、アカウント停止に発展したりするリスクがあります。
- 中国政府に関する政治的発言や批判
- 誇大・虚偽広告と見なされる表現
- 公序良俗に反する内容
- 禁止ワード(SNS上での利用が制限されている単語) など
このような表現は中国特有のコンテキストを理解していないと気づきにくく、日本国内の感覚で投稿してしまうと思わぬトラブルに発展する可能性があります。
そのため、ビジネスで活用する場合には、ガイドラインに準拠した表現・キーワードの選定やクリエイティブ設計が欠かせません。
ポイント②:REDに精通したパートナーと連携する
企業としてREDを活用するなら、中国語や中国のプラットフォーム事情に精通した運用パートナーとの連携が有効です。
例えば、以下のようなサポートを受けられるため、安全かつ成果に直結する運用が可能になります。
- 禁止ワード・表現への事前チェック
- アカウントの安全設計と運用ガイドライン遵守
- 現地ユーザーの感覚を踏まえた投稿設計
- 運用レポートのローカライズ分析
- 現地KOLとの連携支援 など
企業でREDを導入・活用する場合は、専門性のある代行会社のサポートを受けることが最も現実的で安全な方法といえるでしょう。
代行会社の選び方や依頼のメリットについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。
【関連記事】小紅書(RED/レッド)の運用成功は代行会社が鍵?依頼するメリットや選び方も
弊社が支援した小紅書(RED)の運用事例

ここでは弊社が支援した小紅書の運用事例として、テーマパークの事例を紹介します。
|
業種 |
国内の人気テーマパーク施設 |
|
ターゲット |
中国からの観光客・インバウンド層 |
|
支援内容 |
アカウント立ち上げ〜投稿設計・制作・レポート分析 |
|
投稿媒体 |
|
|
目的 |
中国人観光客に向けたブランド認知・来場促進 |
当アカウントでは投稿1本目から、以下のような高い反応を獲得しました。
- いいね:262件
- コメント:64件
- 保存(ブックマーク):52件
初期段階ながら、高いエンゲージメントを獲得しており、ターゲット層への訴求が効果的に機能しています。
現在はフォロワー数700名超、いいね・保存などの反応も累計300件以上と、着実に成果が積み上がっています。
まとめ:使い方に注意すれば小紅書(RED)の危険性は減らせる
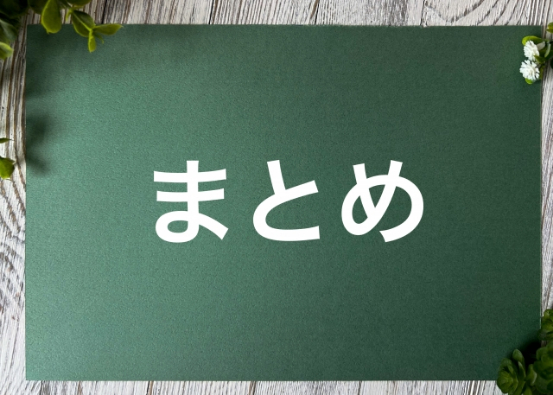
小紅書の運用には注意点もありますが、安全に利用する方法を理解すれば、危険性は減らせます。
正しい方法での利用を心がけ、中華圏向けの集客にうまく活用しましょう。
なお、弊社では、訪日中国人の集客力を向上させるためのRED運用サポートを実施しています。
中国のインバウンド集客および売上拡大を実現したい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
【お役立ち資料】RED 企業アカウント申請書類とチェックリスト
RED(小紅書)の企業アカウント申請書類を、わかりやすいチェックリスト形式でまとめたシートです。
社長の一筆入魂
やっぱり中国のプラットフォームなので、政治的なコンテンツや言い回しはかなりセンシティブです。
REDは台湾や香港の人も見ているので、台湾人や香港人向けに発信するケースもあるんですが、このあたりはとても慎重にいきましょう。(例えば台湾の国旗の絵文字を使うとか、細かいことでも慎重になったほうがよいです)
このあたりの独自のルールやコンプラも、当社の運用サポートは必ずローカルチェックを挟んでいますので、安心してお任せいただけます!

【関連記事】【3ステップ】小紅書(RED/レッド)の企業アカウント作成ガイド!注意点も解説
【関連記事】爆買いは終了?中国人観光客のインバウンド最新動向|おすすめの集客方法も
【関連記事】インバウンド集客ではどのSNSを使うべき?運用成功のポイントも解説
まずはご相談だけでも大丈夫です
お気軽にご連絡ください
さぁ、ご一緒に
はじめましょう。
具体的なご依頼だけでなく、売り方や集客に関することなど現状の課題についても気軽にご相談ください。






