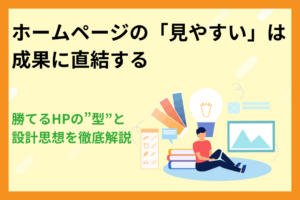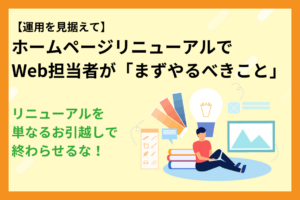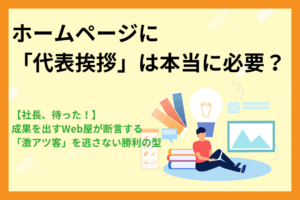-
集客に強いホームページ
-
グラフィックデザイン
グラフィックデザイン -
LINE社認定パートナー事業
-
その他サービス
その他サービス -
会社案内
-
採用・パートナー募集
059-355-3939
受付時間/平日 9:00〜18:00
(土・日・祝を除く)
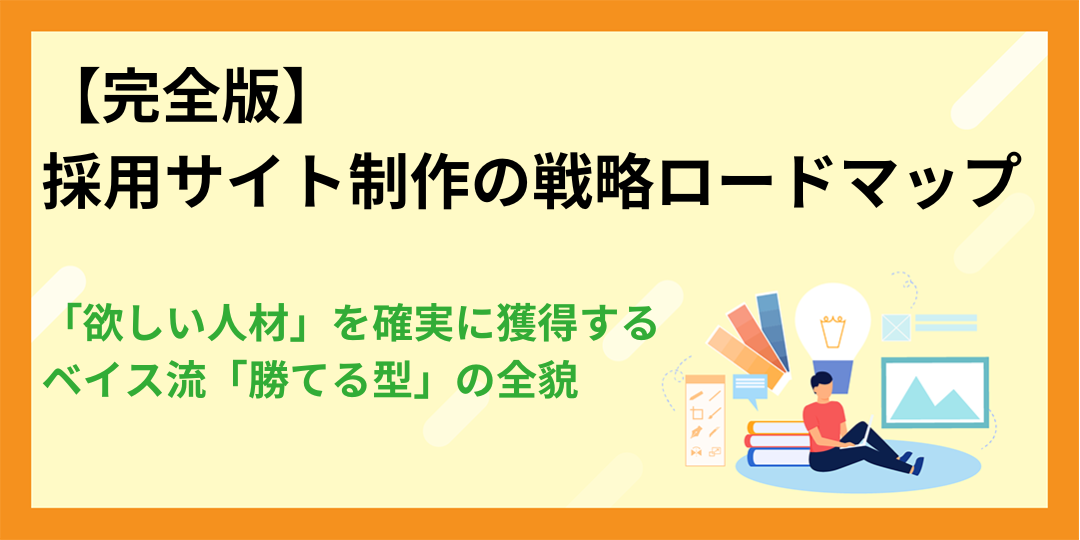
採用サイトの制作・リニューアルを検討している企業では、「デザインやコンテンツづくりなど、やることが多くて、どこから手をつければ良いのか分からない」という担当者の方もいるでしょう。
「とにかく採用サイトの全体像が知りたい」「費用対効果を最大化し、最小投資で採用を成功させる方法はないのか」と悩み、なかなか一歩を踏み出せないケースも少なくありません。
私たちは、ホームページ制作の本質を「つくること」ではなく「効果を出すこと」としてとらえ、一貫して成果(応募というCV)にコミットしてきました。
この視点から考えると、採用サイトは単なる会社紹介ページではなく、「貴社の未来に対する最高の自己投資」です。
この記事は、これまでの私たちのブログで解説してきた「採用サイト成功の各論」を1つのロードマップとして統合した完全版です。
採用サイトの目的設定から応募者を惹きつけるデザインはもちろん、コンテンツ制作の具体的な型まで、私たち独自のノウハウを交えて解説します。
最小投資で欲しい人材を確実に獲得するための具体的な行動指針を見つけたい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
戦略の土台|採用サイトの「目的」と「型」を明確にする

採用サイト制作で必要な最初のステップは、「なぜ、今、そのサイトが必要なのか」という目的を明確にすることです。
目的があやふやなまま制作を始めると、「なんとなくかっこいいサイト」という自己満足で終わり、成果は出ません。
ここでは戦略の土台として考える必要があることを、以下の3つに分けて解説します。
- 採用サイトの目的は「応募者の認知度」で二分可能
- 「大手企業サイトの真似」は最小投資における最大の敵
- 制作前にクライアントに聞きたい最重要の問い
それぞれ詳しく見ていきましょう。
採用サイトの目的は「応募者の認知度」で二分可能
私たちは、採用サイトの役割を貴社に対する応募者の「認知度」によって二分して考えます。
このターゲティングは、制作の難易度や費用はもちろん、依頼すべき業者を決定する際の判断軸にもなります。
具体的な分け方は、下表の通りです。
|
A.既に貴社を知っている人※1 |
B.貴社をまったく知らない人※2 |
|
|
役割 |
「意思決定の加速」 |
「興味関心の醸成」 |
|
ポイント |
|
|
※1 リファラル・社員紹介・企業名検索など
※2 Indeed・広告・業界キーワード検索など
特に、「貴社をまったく知らない人」をターゲットにする場合、その採用サイトは以下に挙げる複数の目的を担う戦略的なWebマーケティングツールとなります。
- 認知度向上
- 理解促進
- CV獲得
最小投資で成果を出すには、この「知らない人」を振り向かせるための戦略的な型が必要です。
採用サイト制作の流れや成功のコツについて知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。
【関連記事】【失敗しない採用サイト制作】「なぜ必要か」から「成功の型」まで、ベイスが導く戦略的Web活用術
「大手企業サイトの真似」は最小投資における最大の敵
採用サイト制作時、多くの担当者が陥る最大の罠が「大手企業サイトのトレース」です。
莫大なブランド力と予算を持つ大手企業は、どのようなデザインでも人が集まります。
そのため、中小企業が同じデザインを真似ても、投資対効果は得られません。
また、大手企業のデザインは「企業の信頼性・安定性の証」として機能しますが、貴社が目指すべきは「自社の本気度・他社との明確な差別化」です。
特に中小企業やベンチャー企業の場合、ブランド力が低い状況で大企業の真似をすることは、自己満足の最たるものといえます。
つまり、中小企業が最小投資で勝つためには、戦い方を変える必要があります。
「誰のどんなTO BEを応援したい会社なのか?誰とどんな未来を作りたい会社なのか?」という、貴社独自の哲学がにじみ出るデザインとコンテンツに集中することが大切です。
採用サイトにおけるデザインの考え方や事例について知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。
【関連記事】【勝てる採用サイトの型】デザインで差をつける!欲しい人材が自ら応募するホームページの設計戦略
制作前にクライアントに聞きたい最重要の問い
私たちが制作前に最も深く掘り下げるのは、「腹の決まり」です。
採用サイトのコンセプトは以下のように、腹の決まりを確かめる問いに対する明確な回答から導かれます。
|
制作前の重要な問い |
意図する効果 |
|
貴社を「知っている人」向けか、「知らない人」向けか? |
予算と戦略の決定 |
|
何を売りにするのか? |
貴社にしかない「専門性や熱量」を言語化 |
|
制作後に「誰を」「何人」獲得したいか? |
「つくること」ではなく「効果を出すこと」へのコミットメントを明確化 |
前述したように、「貴社をまったく知らない人」向けなら、マーケティング戦略としての緻密な導線設計が必要です。
この判断を誤ると、採用にかけるコストが無駄になります。
また、「何を売りにするか」という問いに対する答えは、デザインとコンテンツの核となります。
給与や福利厚生といった条件以外で、求職者のキャリアに何をコミットできるかを明確にしましょう。
さらに、制作後に対する問いは、応募という成果を数値で追うためのKPI設定です。
セッション数や表示回数(=ページビュー)ではなく、CVR(応募率)とLTV(定着率)にフォーカスすることが大切です。
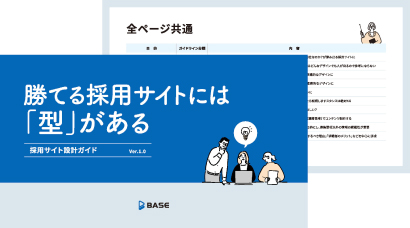
実際の採用サイト制作・運用を通して蓄積した知見から導き出した、成果につながる採用サイトの構成・設計の「型」を開設した秘伝の資料です。
勝てる採用サイトの設計プロセスを凝縮した ▶︎ 勝てる採用サイトの型 をぜひご覧ください。
応募者を惹きつける「デザイン」と「写真」の真実

採用サイトのデザインと写真は単なる「見た目」ではなく、貴社の「本気度」と「リアル」を伝える非言語のツールです。
ここでは採用サイトのデザインと写真について、以下の2つを解説します。
- 「かっこいい」デザインとは「その企業らしさ」である
- 写真は「応募者の不安を取り除く」最重要ツールになる
なお、私たちは「勝てる採用サイトの型」に基づき、貴社の採用課題を深く掘り下げた戦略的なホームページを提案いたします。
「最小投資で採用サイトを成功させたい」「このロードマップにある『型』を自社に適用したい」という方はホームページ制作ページをご覧のうえ、ぜひお気軽にご相談ください。
真実①:「かっこいい」デザインとは「その企業らしさ」である
採用サイトにおける真の「かっこ良さ」とは、その企業らしさがデザインとコンテンツからあふれ出ている状態だと私たちは考えています。
真の意味でのかっこ良さを考えられなければ、その採用サイトは単なる自己満足で終わります。
応募という行動につながる説得力を採用サイトにもたせるためには、以下のような「熱量」や「本気度」についてデザインを通じて求職者に伝えることが必要です。
- 貴社独自の哲学
- 雰囲気
- 自信 など
また、デザインとは「見た目の美しさ」ではなく「成果を出すためのコンテンツの最適化と構造設計」です。
応募という成果につながらないデザインは、無能といえます。
だからこそ、私たちはインフォグラフィック(※)を多用しながら、リズミカルで直感的なデザインを徹底しています。
※情報を図やイラストで表現し、直感的に理解しやすくしたもの
求職者にストレスなく、必要な情報が最短で伝わる設計こそ、私たちが追求するデザインです。
採用サイトにおける「かっこ良さ」とは何か、真の意味やデザイン設計の極意について知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。
【関連記事】【脱・自己満足】「かっこいい採用サイト」が応募につながるメカニズムとは?ベイス流、差別化を生むデザイン設計戦略
真実②:写真は「応募者の不安を取り除く」最重要ツール
採用サイトの写真を「ただの画像」として扱う企業は、採用競争で必ず負けます。
特に、フリー素材やスマホ撮影は最小投資を最大効率で失敗させる原因です。
私たちには独自の経験や自信のほか、「腹が決まっている人」は、その顔つきやまとう雰囲気に決意がにじみ出ているという持論があります。
写真の役割は、この社員の「顔の良さ(自信/熱意/雰囲気)」を最大限に引き出し、求職者に伝えることです。
このとき、撮影用に準備した不自然なシーンではなく、作り込みすぎない自然なカットをプロのカメラマンに撮影してもらうのがポイントです。
以下のような写真1枚1枚から、会社のリアルな「行間」を感じられるよう設計します。
- 業務中の真剣な横顔
- 社員同士が議論している瞬間 など
なお、写真や動画は、ターゲットへのメッセージによって使い分け、配置を決定しましょう。
企業の熱量・雰囲気は動画や躍動感ある写真で、入社後のリアルは自然なスナップ写真で伝えるといった、明確な意図をもって選択するのが理想的です。
動画の多用はテキスト情報への依存を減らし、若手へのアピール力も高められます。
応募につながる写真の選び方について知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。
【関連記事】【写真が採用を成功させる】採用サイトの写真を「応募者を惹きつける強力なツール」に変える設計戦略
応募を加速させる「コンテンツ」の型と極意

応募者が最終的な意思決定を下すのは、「入社後のリアル」が見えたときです。
採用サイトのコンテンツは、このリアルを包み隠さず伝えるための「辞書」であり「ストーリーテリング」の場となります。
ここでは採用サイトのコンテンツづくりにおける極意として、以下の3つを解説します。
- 社員紹介は「応募者を憑依させるストーリー」として設計せよ
- 成功事例は「課題解決のストーリー」として見せる
- コンテンツ設計の普遍的原則(情報の網羅性)を守る
それぞれ詳しく見ていきましょう。
極意①:社員紹介は「応募者を憑依させるストーリー」として設計せよ
求職者は「この会社から買うべきだ(この人たちと働くべきだ)」と確信するために、社員紹介コンテンツを見ます。
そのため、単なるプロフィール紹介でとどめるのではなく、以下のポイントを押さえることが大切です。
- ストーリーに共感させる
- 泥臭い努力を開示する
- 具体的なキャリアパスを示す
転職のきっかけや面接時の印象はもちろん、入社前の不安を正直に語ってもらうことで、応募者は社員に感情移入しやすくなります。
この感情移入こそが、応募に対する最大の動機となります。
また、成功談だけではなく、失敗から学んだ教訓や実際に働いてみて会社に改善してほしいところなども記載しましょう。
「完璧な会社なんてない!」という前提で包み隠さず出し切る姿勢によって、企業の風通しの良さと人間味を表現でき、求職者の信頼を勝ち取りやすくなります。
さらに、キャリアパスでは抽象的な「成長」ではなく、「年収400万→1000万への道」のようなエンタメ感を交えながら提示するのが効果的です。
具体的な年収やポジションの変化を示すことで、入社後の未来を明確に見せます。
管理職や若手社員など複数の視点での社員インタビューも掲載できると、成長の階段をより立体的に表現できるでしょう。
採用サイトにおける社員紹介の重要性や応募意欲を高めるコツについて知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。
【関連記事】【応募率激変】「社員紹介」が会社の採用力を決める!リアルな情報で優秀な人材を惹きつける設計術
極意②:成功事例は「課題解決のストーリー」として見せる
採用サイトの成功事例では、「課題解決から成果に至るまでのプロセス」を学びましょう。
単なる「デザイン集」として真似るのではなく、以下に挙げるような「課題解決のストーリー」を追うことが大切です。
- 最初の課題(応募者数、CV率)がどうだったか
- どのように課題を整理し、どんな型を適用したか
- 最終的に応募数、CV率がどうなったか
また、BtoBや製造業といった硬い業種の場合、事業の成功事例を通じて企業の「熱量」と「人間味」を伝え、応募者の心理的ハードルを下げる工夫が不可欠です。
事例を通じて企業の「熱量」と「雰囲気」を伝え、応募者に「この会社なら自分も成長できる」という確信を与えることが大切になります。
成功にいたるまでの泥臭いプロセスも開示することで、応募者の共感を呼びやすくなるでしょう。
成功事例から学ぶ際の着眼点や具体的な採用サイト例について知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。
【関連記事】【成功事例で学ぶ】応募者を惹きつける「採用サイトの型」とは?ベイス流、課題別デザイン・コンテンツ戦略
極意③:コンテンツ設計の普遍的原則(情報の網羅性)を守る
採用サイトのコンテンツ設計で押さえたいのは、以下の2つです。
- 情報の全部出し切り
- FAQ(よくある質問)の活用
「応募してくれたら説明します」というスタンスは避け、募集要項以外の情報も含めてサイト上で語ることがないレベルで全部出し切りましょう。
求職者の「もっと早く知っていれば」という後悔をなくし、応募率を高めるためです。
特に募集要項ページの量と質は、応募というCV獲得に直結する重要コンテンツとなります。
また、FAQでは「一般的な質問〜少し突っ込んだ質問〜だいぶ突っ込んだ質問」の3カテゴリーに分けて記載するのがポイントです。
他社より劣っていることや、副業・残業といった言いにくいことも包み隠さず出し切ることで、企業の誠実さをアピールでき、信頼感も生まれます。
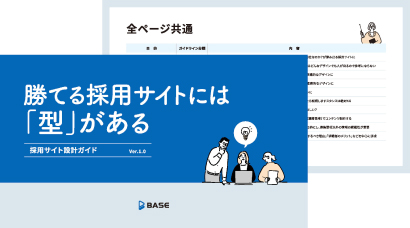
実際の採用サイト制作・運用を通して蓄積した知見から導き出した、成果につながる採用サイトの構成・設計の「型」を開設した秘伝の資料です。
勝てる採用サイトの設計プロセスを凝縮した ▶︎ 勝てる採用サイトの型 をぜひご覧ください。
最小投資で成果を出す「制作フロー」と「パートナー選定」

最小投資で採用サイトを成功させるためには、制作会社と対等に渡り合える「知識」と、「成果にコミットするパートナー」を選び抜く目が必要です。
ここでは、制作フローとパートナー選定について、以下の3つを紹介します。
- 制作前にクライアントに聞きたいこと
- 失敗しない「業者選定」の極意
- 私たちの強み:「勝てる採用サイトの型」と投資対効果
それぞれ詳しく見ていきましょう。
制作前にクライアントに聞きたいこと
私たちが制作前に最も深く掘り下げるのは、「誰のどんなTO BEを応援したい会社なのか?誰とどんな未来を作りたい会社なのか?」という「腹の決まり」です。
「制作前にクライアントに聞きたい最重要の問い」でも紹介したように、採用サイトの制作に着手する際は以下3つの問いに対する答えを明確にしましょう。
- 貴社を「知っている人」向けか、「知らない人」向けか?
- 何を売りにするのか?
- 制作後に「誰を」「何人」獲得したいか?
この「腹の決まり」こそが、Web制作におけるコンセプトの根幹となります。
失敗しない「業者選定」の極意
業者選定における最大のポイントは、「成果へのコミットメント」です。
残念ながら、Web業界には月額管理費をだまし取り、問題を放置し続ける詐欺師のような業者が存在します。
Googleサーチコンソールで検知されているクリティカルなエラーすら放置するような業者に、貴社の採用戦略を任せるのは止めましょう。
実際にAhrefs(エイチレフス)などのツールで自社サイトのヘルススコアを測り、管理業者が機能しているかをチェックしてみてください。
対して、私たちが目指すのはクライアントの成功を「阪神園芸のグランドキーパー気分」で喜べる、真のパートナーです。
私たちは、御社を主役にする「影の立役者」でありたいのです。
クライアントの躍動を「自分の功績」かのように喜べる、徹底した顧客志向を持つパートナーこそが、最小投資を最大効率で活かせます。
私たちの強み:「勝てる採用サイトの型」と投資対効果
私たちは単にデザインやシステムを提供するだけではなく、「勝てるホームページの型」という再現性の高い設計思想を提供します。
最小投資での最大効果を実現するために取り組んでいるのが、以下を中心とした凡事の徹底です。
- 応募者に響く「顔の良さ」を追求した写真・デザイン
- スマホでの直感的なUI/UX(インフォグラフィック多用)
- 失敗談や改善点含む情報の全部出し切り など
また、借金をしてでも事業に投資すべきという代表の思想を、採用サイト制作という「投資」に当てはめ、投資対効果の最大化にコミットします。
私たちは、「つくること」ではなく「効果を出すこと」が目的であることを、制作の最初から最後まで貫きます。
Webが苦手な経営者でも、安心して任せられるパートナーでありたいと強く願いながら、日々の制作や運用サポートに取り組んでいるところです。
まとめ:採用サイトは最高の「自己投資」である

採用サイト制作は、費用対効果を追求すべき最高の「自己投資」です。
単に情報を羅列した採用サイトではなく、「貴社の本気度」や「社員のリアルな顔の良さ」などを包み隠さず開示することが、最小投資で欲しい人材を確実に獲得する鍵となります。
このロードマップと私たち独自の「型」を参考に、貴社の採用サイトを「応募を加速させる戦略ツール」へと変革させてください。
投資対効果を最大化する「ホームページ制作」のご相談はこちら
私たちは、採用サイト制作を「つくること」ではなく「効果を出すこと」として、貴社の採用課題を深く掘り下げた戦略的なホームページを提案いたします。
「最小投資で採用サイトを成功させたい」「このロードマップにある『型』を自社に適用したい」という方はホームページ制作ページをご覧のうえ、ぜひ一度ご相談ください。
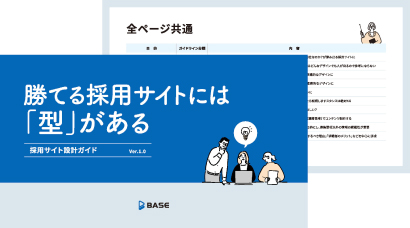
実際の採用サイト制作・運用を通して蓄積した知見から導き出した、成果につながる採用サイトの構成・設計の「型」を開設した秘伝の資料です。
勝てる採用サイトの設計プロセスを凝縮した ▶︎ 勝てる採用サイトの型 をぜひご覧ください。
社長の一筆入魂
企業の採用サイトを制作する時にはまず「誰が、どうなれる会社なのか」。
これを考えます。
応募を検討してる、まさに今採用サイトを読んでいる人が、具体的にどう昇華される職場環境なのか。
この視点で採用コンテンツをつくるように心がけています。
実は、自社の本当の魅力は、内側にいると見えにくいものです。
今はまだ採用の勝ち筋が見えない企業も、我々にご相談いただければ、必ず「光」を見つけ出します。
ぜひご相談ください!

【関連記事】【ホームページ】改修かリニューアルか?費用と判断基準を解説
【関連記事】【事例付き】UI/UXとは?コンバージョンを最大化する設計時のポイントも解説(スマホ最適化編)
【関連記事】成果を出すホームページメニューの絶対法則
ホームページ制作はいい業者との
出会いが8割です
実績数
解析力
伝達力
を兼ね備えた当社に是非一度ご相談ください

まずは御社の商材のファンになることから始めたいので、お問い合わせいただき御社のことを教えてください。
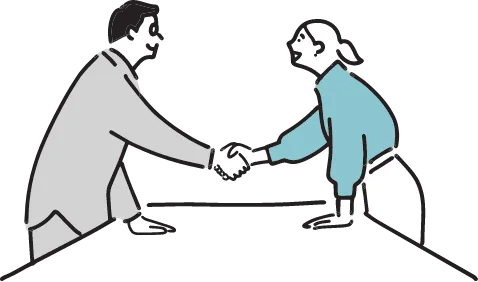
さぁ、ご一緒に
はじめましょう。
具体的なご依頼だけでなく、売り方や集客に関することなど現状の課題についても気軽にご相談ください。