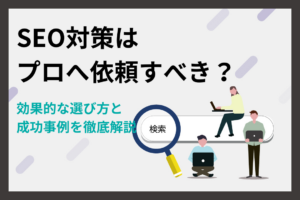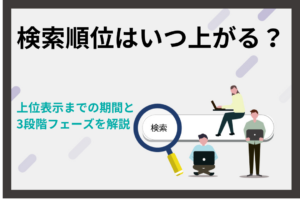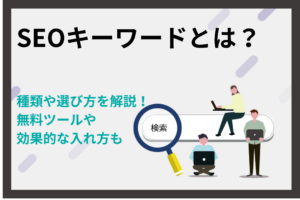-
集客に強いホームページ
-
グラフィックデザイン
グラフィックデザイン -
LINE社認定パートナー事業
-
その他サービス
その他サービス -
会社案内
-
採用・パートナー募集
059-355-3939
受付時間/平日 9:00〜18:00
(土・日・祝を除く)
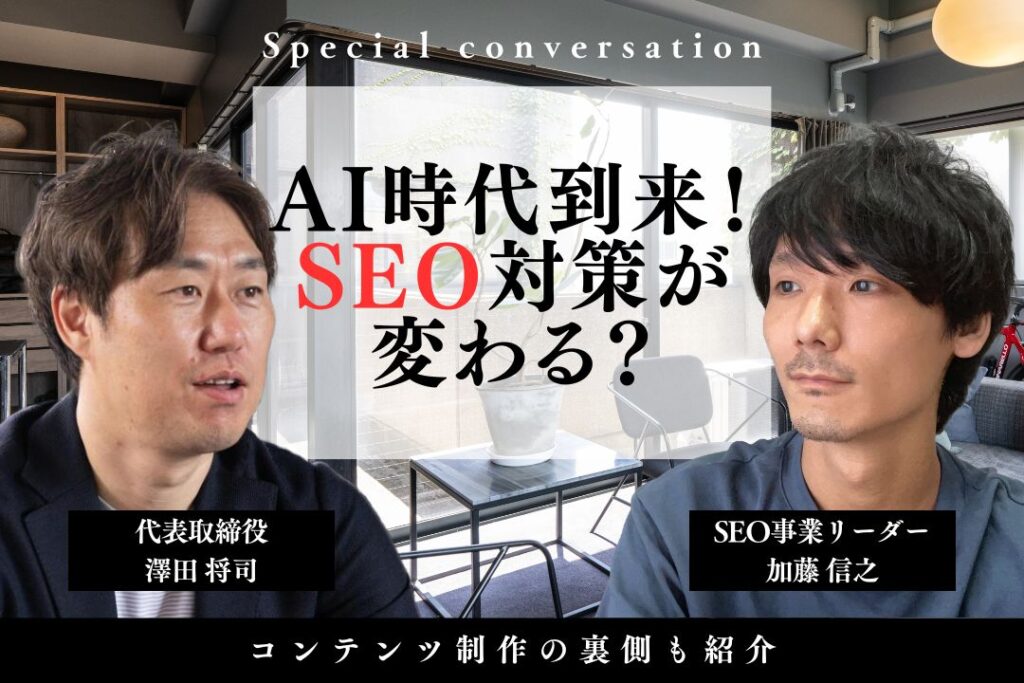
SEO対策は、潜在顧客から顕在顧客まで幅広いユーザーにアプローチできるWebマーケティング施策です。
近年ではAIを使った「施策の効率化」が図られるケースも多くなっていますが、成果を上げるためには属人的な努力がいまだ欠かせない状況です。
この記事では弊社の代表取締役「澤田 将司(以下:澤田)」とSEO戦略事業部チームリーダー「加藤 信之(以下:加藤)」の対談をもとに、AI時代のSEO対策・コンテンツ制作で大切にしたいことを解説します。
実際にAIを使ったコンテンツの成果についてもあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
AI時代のSEO対策で重視すべきこと
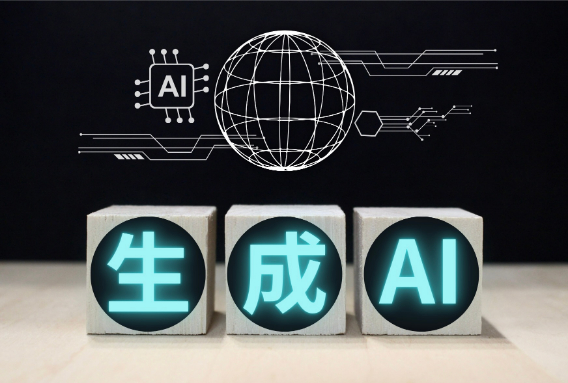
最近では、SEOの分野にもAIがかなり入り込んできている印象があります。
検索するとAIが結果を生成する、いわゆるゼロクリック検索の影響は見逃せないですよね。
とはいえ、検索エンジンとしては確実な情報をソースとしたいわけですから、E-E-A-T(※)のある記事はAI時代においても重要になってくると思います。
※※Googleの評価基準である「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字を取ったもの
「この検索キーワードだったら、この会社のこのページを持っていっておけば、間違いないだろう」という、権威性や専門性が高い記事であれば、AIも取り上げたくなりますよね。
自社データをエビデンスにしているなど、独自性のあるコンテンツも引き続き重要です。
最近のSEO対策では、オリジナル情報を積極的に取り入れて上位表示を目指す流れがあります。
それをやっていくことで、AIに対しても自然に対策できるというイメージですね。
そうですね。
ユーザー側からしたら、AIは「より検索意図を理解して、最適な情報を出してくれるアシスタント」です。
だからこそ、作り手側はそのアシスタントに選ばれるように、E-E-A-Tをより重視したコンテンツを制作することが大切だと思います。
SEO対策の基礎知識や基本的なやり方について振り返りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。
【関連記事】【初心者向け】上位表示させるSEO対策のやり方!具体例や注意点も解説
AIで制作したコンテンツは成果が上がりにくい?

ここでは、AIを使ったコンテンツ制作の裏側として以下の2つを紹介します。
- 【結論】エンゲージメント率は低い
- 成果が上がりにくい理由
それぞれ詳しく見ていきましょう。
【結論】エンゲージメント率は低い
「AIであれば無限にコンテンツを生成できるだから、制作もすべて任せても良いのでは」と言われることがあります。
ただ、AIを使って制作したコンテンツが最終的に売り上げにつながるかと聞かれると、僕は結構疑問です。
AIで生成できるということはつまり、収集できる範囲の情報を使っていることを意味します。
僕も自分自身のSNSでAIを使って書いたものをレタッチしている投稿もありますが、実はエンゲージメント率が低いんです。
ネタやエビデンス、結び方などをきちんと指示しているにもかかわらず、100%自分で書いた投稿とはまったく反応が違います。
それは興味深いですね。
なぜ反応が異なるのかは、正直まだうまく言語化できていません。
ただ、古い言葉で言うと、AIを使った言葉は「魂を持っていない」のではないかと思います。
成果が上がりにくい理由
澤田さんの投稿を見ている1人のユーザーとしては、AIを使っているとは感じませんでしたが……。
最後の仕上げとしてのレタッチは自分でしているので、僕が書いた風にはなっているとは思います。
ただ、ChatGPTなどのAIは基本的に、「次は、このワードが来る確率が高いよね」という考え方で文章を生成していくわけですよね。
そうした文章は、なぜかSNSで「いいね」などの反応が少なくなるんですよ。
言葉遣いなどの細かいところに、人間味の有無を感じるのでしょうか。
「澤田さんは、こういう言い回しはしないよね」という違和感が無意識下で起きるのか、僕自身もまだ検証中です。
SNSではこのような傾向にありますが、SEOはもちろん、YouTubeも上位表示を取るという意味では一緒です。
実際、ショート動画ぐらいだったら、AIで余裕で作れてしまう世界になっています。
しかし、それが果たしてコンテンツとして伸びるか、売り上げにつながるか、もとをただせば、「ユーザーがE-E-A-Tを感じてくれるか」というところはやはり疑問です。
弊社のSEO対策では1記事1記事ライターさんに発注して、お金と時間を使いながらコンテンツ制作していますが、そっちの方がまだ良いと感じます。
SEOコンテンツの制作手順やコツについて知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。
【関連記事】SEOコンテンツとは?制作の流れを解説!売上アップにつながるコツも紹介
AI時代のコンテンツ制作で大切にしたいこと

AI時代のコンテンツ制作で大切にしたいことについて、以下2つの視点で解説します。
- 企業側で大切にしたいこと
- SEO業者で大切にしたいこと
なお、SEOで重要なキーワード選定のコツやAI時代で生き残るためのポイントについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。
【関連記事】SEOはキーワード選定が鍵!コンバージョン率を伸ばすノウハウも紹介
企業側で大切にしたいこと
AI時代の検索結果対策は必要ですが、もっと本質的なところを突き詰めると、「自社で埋もれているコンテンツを愚直に出していく」という姿勢が大切だと思います。
遠回りのような気がして結局は近道のような……その道のプロが時間をかけて絞り出していく工程が、かえって「今のAI時代におけるコンテンツ制作」になってきていると感じます。
逆に、「AIに書かせて圧勝しました」というストーリーは、あまり思い浮かびません。
とはいえ、AIをまったく使うなという話ではなく、活用シーンの見極めが重要になると思います。
例えば、できあがった文章をチェックしてもらって、コンプライアンス違反になるような言い回しを発見・修正するといったことがAIは大得意です。
コンテンツそのものを作らせる以外の場面でAIを活用したほうが、効率と成果の双方を上げやすくなると考えます。
SEO業者側で大切にしたいこと
昔のSEO業者はいわゆるブラックハットSEOと言って、抜け穴や裏技をクライアントに教えることでお金をもらっていました。
しかし、今はブラックハットSEOの価値がなくなり、SEO業者とクライアントが持っている情報に差はありません。
では何が求められるか、加藤さんの言葉を借りながら表現すると「企業に眠る情報のコンテンツ化して、正しいユーザーに届けるお手伝いをする」というイメージになりますね。
そうですね。
逆に言うと、検索エンジンの上位表示を取ることだけを目標としたSEO業者は単価が下がっていくでしょう。
LPの最適化やCV改善の提案なども含めてどのくらいの価値になるのかが、SEO業者の比較検討時、より重視されるようになると思います。
【余談】今のSEO業界に足りないのはこれだ!

最後に余談として、今のSEO業界に足りない要素について解説します。
- エコシステムのデザインと実行ができる人
- 単なる作業者では生き残れない
それぞれ詳しく見ていきましょう。
エコシステムのデザインと実行ができる人
「SEOはこの企業」「LPはあの企業」というよりは、全部まとめて対応してくれたほうがクライアント側の工数も減りますよね。
そうなんですよ。
それに、例えばどのような意図でこのSEO対策を施したのか、LPを制作した会社が100%理解しているかというと、していないと思います。
効率と成果の双方を上げたいクライアントからすると、一気通貫でデザインしてくれるSEO業者は非常に価値が高くなりますね。
個人的にも、SEOだけでクライアントのビジネスに大きなインパクトが与えられる感覚は、なくなってきています。
SEO以外の施策も含めて、Webマーケティングの全体像をデザインして戦略を見れる力が、より一層重要になってきそうです。
それができるWebマーケターは、まだ多くないですからね。
結局のところ、指名検索をたくさん取ってドメイン評価が上がれば、SEOにも好影響を与えます。
指名検索をどのように取るのか他の施策と組み合わせながらデザインして、ビジネス全体を成長させれば、回り回ってSEO対策になる……このエコシステムをデザイン・実行できる人が、今後増えていってほしいですね。
単なる作業者では生き残れない
キーワードによっては、検索結果画面にYouTubeの動画やGoogleの地図が出ることもあります。
つまり、「SEO=記事コンテンツの制作」ではなくなってきているということです。
効果的な動画の制作やMEO対策の知識などもそろってこそ、現代のSEOマスターといえます。
「クライアントの事業を成長させるためには、何が必要か」という視点は、忘れたくないですね。
その視点が抜けると、ひどい言い方をしたら「単なる作業者」としてしか見られなくなり、当然単価も上がりません。
デザイナーさんもクライアント視点が抜けた職人芸に陥りやすいので、要注意です。
長く安定して活躍するためにも、代わりがきく「作業者」から「戦略パートナー」へと成長したいところですね。
まとめ:AI時代だからこそユーザー目線のSEO対策が大切

SEO対策はAI時代でも引き続き必要ですが、ユーザー目線を大切にしたE-E-A-Tのある記事がより一層重要になってきます。
便利だからといってAIに頼りきりとなるのではなく、適材適所を意識した上手な使い方で、コンテンツ制作の効率と成果を上げていきましょう。
なお、弊社では月額5万円から始められるSEO対策サポートサービスを展開しております。
Web広告やLINE運用などSEO対策と同時に進めることで集客力・追客力を上げる施策も、プロが支援いたします。
自社ホームページを通じて売上を拡大させたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
【関連記事】SEOにおける「被リンク」の重要性とは?良質なリンクの獲得方法も解説
【関連記事】コーポレートサイトのSEO対策とは?主な方法や成功事例を解説!
【関連記事】コーポレートサイトブログとは?書くメリットや注意点を解説|成功事例も
ご相談だけでも大丈夫です
お気軽にご連絡ください
さぁ、ご一緒に
はじめましょう。
具体的なご依頼だけでなく、売り方や集客に関することなど現状の課題についても気軽にご相談ください。