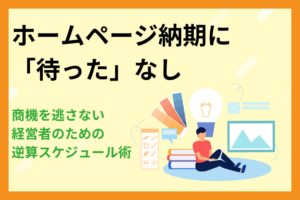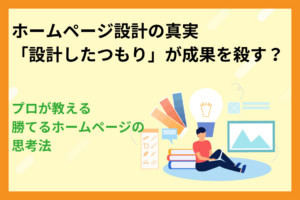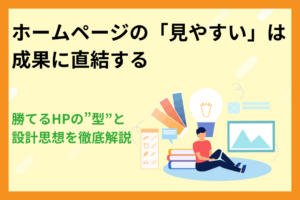-
集客に強いホームページ
-
グラフィックデザイン
グラフィックデザイン -
LINE社認定パートナー事業
-
その他サービス
その他サービス -
会社案内
-
採用・パートナー募集
059-355-3939
受付時間/平日 9:00〜18:00
(土・日・祝を除く)
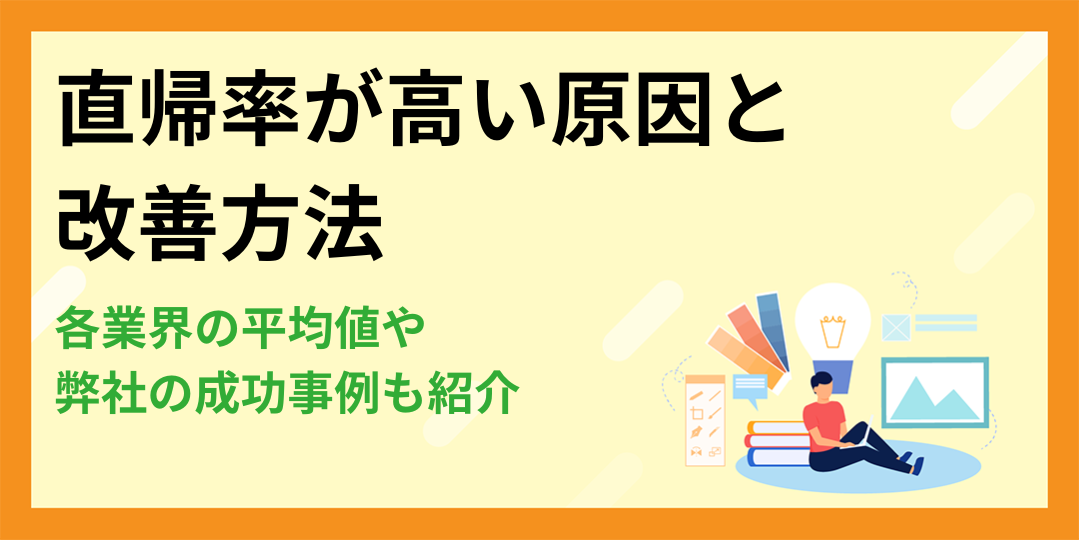
ホームページの運用において、直帰率は重要な指標の1つです。
直帰率が高い場合、ホームページに多くのユーザーが訪問していても、問い合わせや売上につながりません。
しかし、「そもそも直帰率とは具体的に何を意味するのか」「高い場合はどのように改善すれば良いのか」と疑問に思う方も多いでしょう。
この記事では、直帰率の意味や高い場合の改善方法を解説します。
直帰率が高くなる原因や、弊社が数値を大幅に改善した成功事例も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
直帰率とは

直帰率とはホームページを訪問したユーザーが、最初のページのみを見て閲覧を終了した割合のことです。
この割合が高い場合、ユーザーの期待とページ内容にギャップがあり、改善が必要な可能性を示しています。
例えば、お客様がレストランに入店したものの、イメージする雰囲気と合わずにそのまま帰ってしまう状況と似ています。
なお、GA4(Googleアナリティクス4)における直帰率は、従来の計測方法とは異なります。
GA4での直帰率とは、サイトに訪問したユーザーがエンゲージメントを発生しないまま離脱したセッションの割合です。
エンゲージメントとは、10秒以上のページ滞在、コンバージョンイベントの発生、2回以上のページビュー(またはスクリーンビュー)のいずれかを満たしたセッションのことです。
つまり、GA4では、1ページしか見なかったとしても、10秒以上滞在したり、コンバージョンが発生したりすれば直帰とはみなされません。
このGA4の定義を理解したうえで、直帰率の改善策を検討することが重要です。
直帰率を正しく改善するためには、以下の2点についての認識が必要です。
- 直帰のパターン
- 各業界の平均値
それぞれ詳しく見ていきましょう。
直帰のパターン
直帰率の改善には、ユーザーのどのような行動が直帰として計測されるのかを理解しておくことが重要です。
直帰は離脱の一種ですが、それぞれ課題は異なるため、ユーザー動向を分析する際は区別して確認することが必要です。
なお、Googleアナリティクス4(GA4)における直帰の定義は、従来の「1ページのみ閲覧してサイトを去る」から変更されました。
具体的には、サイトに訪問したユーザーが、以下のエンゲージメントが発生しないまま離脱した場合に直帰とみなされます。
- 10秒以上のページ滞在
- コンバージョンイベントの発生
- 2回以上のページビュー
逆に言えば、1ページしか見なかったとしても、10秒以上滞在したり、コンバージョンが発生したりすれば直帰とはみなされません 。
直帰率の改善にはユーザーが期待する情報に素早くアクセスできるよう、ページ内容と導線を最適化することが大切です。
なお、直帰率と似た指標に「離脱率」があります。
離脱率とは、ユーザーがホームページを訪れて、そのページの閲覧が最後になった割合を指します。
直帰は離脱の一種ですが、それぞれ課題は異なるため、ユーザー動向を分析する際は区別して確認することが必要です。
各業界の平均値
下表は、当社が調査した業界別の直帰率データです(当社調べ/2024年5月〜2025年5月の期間に6サイトを計測)。
|
トップページ |
商品・サービスページ |
会社案内 |
|
|
ウェブ業界 |
21.18% |
39.18% |
26.94% |
|
不動産業界 |
25.23% |
33.62% |
21.82% |
|
葬儀業界 |
19.53% |
13.42% |
15.51% |
|
観光業界 |
13.49% |
8.48% |
ー |
|
住宅業界 |
26.05% |
16.45% |
10.1% |
|
製造業界 |
21.49% |
12.57% |
13.21% |
|
全業界の平均値 |
21.16% |
20.62% |
17.53% |
緊急性の高い葬儀業界は、サービス内容などを熟考するため直帰率が低い傾向です。
一方、高額な買い物の不動産は、慎重な比較検討により商品・サービスページが高い割合となっています。
このように、直帰率はユーザーの求める情報や訪問目的によって大きく左右されます。
なお、直帰率の計算方法は、以下の通りです。
▼計算方法
|
直帰率=直帰数÷セッション(訪問)数×100 |
実際の計測には、GA4(Googleアナリティクス4)といった計測ツールを活用するのが一般的です。
GA4は、Googleが提供するアクセス解析の分析ツールとなり、ユーザーの行動を可視化できます。
直帰率を改善するには、業界ごとの平均値を把握するだけでなく、正確な計測による分析が不可欠となっています。
「直帰率が高い=問題があり改善が必須」とは限らない?

直帰率が高い状態は、必ずしも問題がないとはいえません。
たとえユーザーが最初のページで求めている情報を得られたとしても、そのページから他のコンテンツへと誘導できていないことは、ビジネス機会の損失につながる可能性があります。
そのため、直帰率が高いページは、常に改善の余地があると考え、ユーザーの行動を分析することが不可欠です。
ユーザーが満足したうえで離脱しているのか、それともコンテンツに不満を感じて離脱しているのかを正しく見極め、適切な改善策を講じることでサイト全体の成果向上を目指しましょう。
例えば、美容院の営業時間のみ確認したいとき、ホームページで該当するページを見れば目的は達成されます。
このような場合の直帰は、自然な行動といえるでしょう。
直帰率が高いページの中でも優先的に改善したいのは、以下のようなページです。
- ランディングページ(LP)
- コンバージョン(CV)につながるページ
- コンバージョン率(CVR)を向上させたいページ
- 表示回数(=ページビュー)が多いページ
LPは、広告などから流入したユーザーを着地させるページとなり、特に直帰率の管理が重要です。
CVとは、商品の購入やお問い合わせといったユーザーの行動を示し、CVRは成果に至った割合をいいます。
上記のような、ホームページの成果に関わるページで直帰率が高い場合でも、適切な分析と改善によってCVRの向上が期待できます。

編集部
ベイスでは、運用性の向上を目的として、「Googleアナリティクス」や「Googleサーチコンソール」などの計測用タグを導入しています。
効率的な運用と正確なデータ取得の実現に向けて、Googleタグマネージャー(GTM)による一元管理も行っているところです。
なお、CVRの計算式や弊社が実践した改善方法を詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。
【関連記事】広告運用等で重要なCVRとは?計算式や平均値を紹介!弊社の改善方法も解説
直帰率が高いときの3大原因と改善方法

直帰率が高いときの主な原因は、以下の3つです。
- ユーザーニーズを満たせていない
- ユーザーにストレスを感じさせてしまう
- 次に起こすアクションが分かりにくい(ファーストビューにCTAがあれば、複数ページビューやコンバージョンを誘発できる)
なお、弊社は500社を超える企業サイトの解析結果を基に生みだした「ホームページの型」を活用し、成果につなげる改善を実践しています。
直帰率が高くて不安な方は、ベイスが原因分析から改善提案までサポートいたします。
ホームページ制作ページをぜひ一度ご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。
原因①:ユーザーニーズを満たせていない
直帰率が高くなる最大の原因は、コンテンツがユーザーニーズを満たせていないことです。
ユーザーは明確な目的を持ってホームページを訪れるため、期待した情報が見つからないと、即座に閲覧を中断してしまいます。
例えば、タイトルが「簡単ダイエット」なのに綿密な食事療法と数時間行うトレーニングの見出しが続いていれば、ユーザーは直帰してしまうでしょう。
直帰率を改善するためには、検索KWとページの内容を一致させ、ユーザーが瞬時に価値を理解できる構成が必要です。
原因②:ユーザーにストレスを感じさせてしまう
ユーザーにストレスを感じさせてしまうことも、直帰率が高くなる原因の1つです。
ホームページのデザイン崩れやスピードの遅さは、見にくさや読みにくさを生み、直帰につながります。
このようなストレスを軽減して直帰率を改善するには、ユーザーインターフェース(UI)とユーザーエクスペリエンス(UX)の向上が重要です。
UIはユーザーが直接触れるボタンやレイアウトを指し、UXはサービスや商品から得る体験を意味します。
適切な対策を講じれば、ユーザーはストレスなく他のページに遷移でき、直帰率の改善が期待できるでしょう。

編集部
ベイスでは、ユーザーのUI/UX向上を目的に「高速表示の対応」を基本としています。
ユーザーの待つストレスを排除するには、WebPによる画像の軽量化やLazyloadでの読み込み最適化など、適切なツールの活用が大切です。
さらに、グローバルメニューは7つまでに制限することで、選択にかかる精神的負荷の軽減によってUI/UXの向上を図っています。
なお、ホームページの表示速度が重要な理由や改善方法を詳しく知りたい方は、下記の記事をチェックしてください。
【関連記事】ホームページの表示速度が遅いと売上に大ダメージ?測定・改善の方法を解説
原因③:次に起こすべきアクションが分かりにくい
ユーザーが次に起こすべきアクションを分かりやすく示していないことも、直帰率が高くなる原因となります。
ページを閲覧して興味を持ったユーザーが、「購入」などのアクションに移りたい場合、CTA(※)がなければ直帰する可能性があります。
※購入や申し込みといった行動につながるボタン
内部リンク先やCTAといった適切な導線が、直帰率の改善とCV率の向上を実現するためには重要です。

編集部
ベイスでは、「記事末尾に関連する自社サービスページへのリンクや無料相談CTAを設置する」ことも基本構造として徹底しています。
記事内容との関連性を重視し、ユーザーが自然にアクションを取りたくなる導線設計がポイントです。
なお、サイト導線に関する設計時のポイントや成功事例を詳しく知りたい方は、下記の記事をチェックしましょう。
【関連記事】【成功事例付き】サイト導線とは?重要な理由や設計時のポイントを解説
【独自ノウハウも】直帰率を改善した弊社の成功事例

弊社は、数百社のホームページ制作・運用に基づいて「型」を生み出しました。
その型を活用し、弊社がホームページ制作ページに関する直帰率を改善した事例についてご紹介します。
以下は、弊社が改善した直帰率の変化です。
|
改修前(2025年3月) |
20% |
|
改修後(2025年5月) |
16.67% |
従来は直帰率が20%代で推移していたため、ユーザーが次に何をするかを明確にし、他のページへ遷移しやすい設計構造へと改善しました。

編集部
下表は、実際に施した改修内容を抜粋したものです。
|
ページ種類 |
目的 |
具体的な内容 |
|||||||||
|
詳細ページ |
コンバージョン獲得 |
ユーザーが最初に見るファーストビューエリアにCTAを設置 |
|||||||||
|
常設ページ |
離脱率の低減 |
コンテンツ読了後の導線として、末尾に必ずCTAと関連ページへのリンクを設置 |
|||||||||
|
入力フォーム |
UI/UXの向上 |
複数ページのフォームを1ページに集約し、ユーザーの入力負荷を軽減 |
|||||||||
この「ホームページの型」に基づいた改修により、1か月で3.33%の大幅な改善を実現しています。
ホームページの成果を確実に上げたい方は、無料でのお問い合わせも受け付けているので、ぜひお気軽にご相談ください
まとめ:CVRを向上させたいなら直帰率も改善しよう

直帰率が高いページは、SEO的にもCV的にも評価されにくく、ユーザーにとっての価値が伝わっていない証拠といえます。
これを適切に改善してCVRの向上を図るには、ユーザー行動の分析と戦略的な設計といった、専門知識や技術が不可欠です。
弊社は、500社を超える支援で培った実績により、長期的な成果につながるホームページ制作をサポートしています。
直帰率の目安から大きく外れているような場合でも、最適な構造を設計して数値改善を実現します。
CVRの向上につながる直帰率改善を目指したい方は、ぜひ一度ホームページ制作ページをご覧ください。
【関連記事】【事例付き】ホームページのトップページに関する基礎知識|大切な役割や評価指数も解説
【関連記事】ホームページのリニューアルを成功させるポイント!進め方や費用・事例も
【関連記事】企業ホームページの構成で押さえたい8つのポイント!業種別の事例も解説
ホームページ制作はいい業者との
出会いが8割です
実績数
解析力
伝達力
を兼ね備えた当社に是非一度ご相談ください

まずは御社の商材のファンになることから始めたいので、お問い合わせいただき御社のことを教えてください。
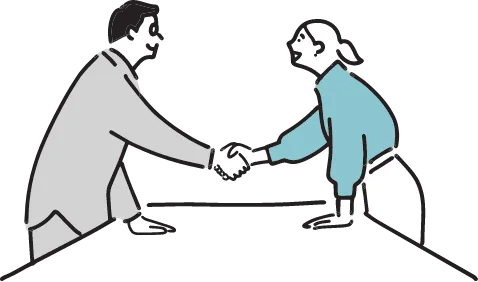
さぁ、ご一緒に
はじめましょう。
具体的なご依頼だけでなく、売り方や集客に関することなど現状の課題についても気軽にご相談ください。