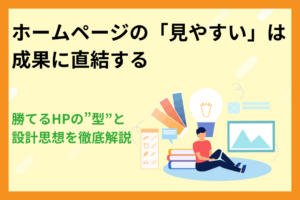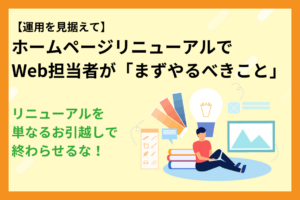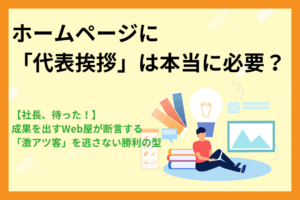-
集客に強いホームページ
-
グラフィックデザイン
グラフィックデザイン -
LINE社認定パートナー事業
-
その他サービス
その他サービス -
会社案内
-
採用・パートナー募集
059-355-3939
受付時間/平日 9:00〜18:00
(土・日・祝を除く)
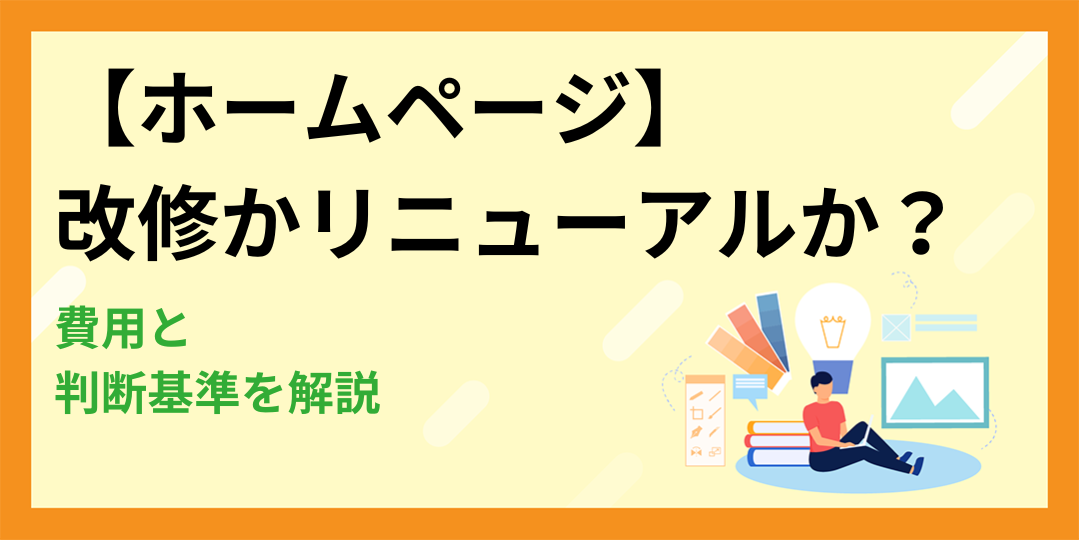
弊社では、中小企業の経営者やWeb担当者の方から「ホームページをなんとかしたいけど、全面リニューアルするほどの予算や時間はない」といったご相談をいただくことがよくあります。
「なんとなく時代遅れに感じるから作り直したいけど、本当に必要なのか分からない」という方も多いでしょう。
ホームページは、まさに会社の「顔」であり、Webマーケティングの「心臓部」です。
しかし、ただ漠然と「古くなったから」という理由で多額の費用をかけてリニューアルするのは、賢明な判断とはいえません。
この記事ではホームページの「改修」と「リニューアル」の違いを明確にし、あなたのビジネスにとって最適な選択肢を見つけるための判断基準と具体的な方法を解説します。
ホームページ改修にかかる費用相場についてもあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
ホームページ改修とリニューアル、どちらを選ぶべき?

「改修」と「リニューアル」はどちらもホームページを改善する施策ですが、下表のようにさまざまな点で違いがあります。
|
項目 |
ホームページ改修 |
ホームページリニューアル |
|
目的 |
特定の課題解決
|
|
|
規模 |
ページの一部、または特定の機能に絞った変更 |
サイト全体のデザインやコンテンツ、システムを一新 |
|
費用 |
比較的安価(数万円~数十万円) |
高額になりやすい(数十万円~数百万円) |
|
期間 |
短期間(数日~1ヶ月程度) |
長期間(数ヶ月~半年以上) |
|
リスク |
低い |
高い |
この違いを理解することが、適切な判断を下すための第一歩です。
改修は、家に例えるなら「部屋の壁紙を張り替える」「キッチンの蛇口を交換する」といった、既存の構造を活かした部分的な改善です。
これに対して、リニューアルは「柱や基礎から全面的に建て替えを行う」という、家全体の構造や機能を根本から見直すことを指します。
ここではホームページの改修・リニューアルの基礎知識として、以下の3つを解説します。
- ホームページ改修とは
- ホームページリニューアルとは
- 改修とリニューアルの判断基準:あなたの目的とコスト効率
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ホームページ改修とは
ホームページ改修とは、デザインやコンテンツなどを部分的に修正・変更することです。
例えば、以下のような取り組みがホームページ改修にあたります。
- 特定ページの画像を差し替える
- お問い合わせフォームの文言を変更する
- SEO対策として記事コンテンツを追加する など
コストと時間を抑えつつ、特定の課題にピンポイントで対応できる点が大きなメリットとなります。
ホームページリニューアルとは
ホームページリニューアルとは、サイト全体のデザインやコンテンツだけではなく、基盤となるシステム(CMS※やサーバー)を根本から作り直すことです。
※プログラミングの専門知識がなくとも、ホームページを編集・管理できるシステム
リニューアルは大規模なプロジェクトになるため、費用も期間もかかります。
しかし、抜本的な課題解決やブランディングの再構築を図りたい際には最適な選択肢です。
単に見た目を変えるだけではなく、構造自体を見直し、新しいマーケティング戦略にあわせて再構築することが大切です。
リニューアルの進め方や成功事例について知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。
【関連記事】ホームページのリニューアルを成功させるポイント!進め方や費用・事例も
改修とリニューアルの判断基準:あなたの目的とコスト効率
弊社では「改修」で済むのか、「リニューアル」が必要なのかは、以下に挙げる3つを踏まえて判断しています。
- 目的
- ホームページの現状
- 費用対効果
弊社は、「なんとなくリニューアル」を安易に推奨しません。
重要なのは、「ホームページに投資する費用が、将来的にどれだけの売上となって返ってくるか」という費用対効果です。
まずは、現状のホームページが抱えている「課題」をデータに基づいて特定し、その課題を解決するための最適な手段を考えましょう。
具体的にどのようなケースが当てはまるか、以下の2つを見ていきましょう。
- 改修で十分なケース
- リニューアルを検討すべきケース
なお、弊社ではお客様の課題をヒアリングし、データに基づいたホームページ制作・運用を強みとしています。
改修とリニューアルのどちらが自社に最適か知りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
改修で十分なケース
改修で十分なケースの例は、以下の通りです。
- 特定のKPI(※)を改善したい
- コンテンツの一部を最新の情報に更新したい
- 軽微なデザインの調整を行いたい
- 予算や期間を抑えたい
※コンバージョン率や直帰率など
特にKPIで着眼すべきポイントは、「どこで血流が止まっているか」を分析することです。
例えば、「TOPページからの遷移率が低い」「特定の商品ページのCVRが著しく低い」といった具体的な課題が見つかった場合、部分的かつ集中的な改修で大きな成果が期待できます。
Googleアナリティクスなどのツールを活用しながらユーザーの行動データを深く掘り下げ、改修の着眼点を絞りましょう。
リニューアルを検討すべきケース
リニューアルを検討すべきケースは、以下の通りです。
- ブランドイメージを根本的に刷新したい
- ビジネスモデルが大きく変化した
- 現在のシステムが古く、機能拡張が難しい
- 複数のページにまたがる大規模な問題がある
- ホームページ全体でユーザー体験を抜本的に改善したい
特に、古いCMSや独自システムを使っている場合、新しい機能を追加したくとも技術的に困難なケースがあります。
このような場合はセキュリティリスクも高まるため、リニューアルを選択したほうが賢明であるといえるでしょう。
【目的別】ホームページの改修で成果を出す方法

ここからは以下5つの具体的な改修目的別に、ベイスが提案する効果的なアプローチを紹介します。
- 検索結果画面からの流入を増やしたい
- コンバージョン(CV)数を増やしたい
- デザインを刷新したい
- 使いにくさを改善したい(UI/UXの向上)
- 運用の効率を上げたい
それぞれ詳しく見ていきましょう。
改修の目的①:検索結果画面からの流入を増やしたい
検索流入を増やすには、SEO対策が不可欠です。
ホームページ改修においては既存ページのコンテンツを強化したり、新たなコンテンツを制作・追加したりといった対策が有効になります。
また、AI時代で勝ち残るためには、LLMO(大規模言語モデル最適化)対策が必要です。
Googleの「AI Overvie(AIO)」や「People Also Ask(PAA)」への掲載を狙うには、ユーザーのあらゆる疑問を解決する網羅性の高いコンテンツが求められます。
具体的なLLMO対策として、下表の2つを押さえておきましょう。
|
構造化マークアップ |
記事の内容を検索エンジンやAIに正確に伝えるための基本的なLLMO対策 |
|
llms.txt |
検索エンジンのクローラーを制御するrobots.txtと同様に、AIクローラーの制御に役立つ対策 |
これらの対策を講じることで、AI時代の検索結果でも上位表示されやすくなります。

編集部
近年、ホームページの集客力を高めるうえで、SEO(検索エンジン最適化)とLLMO(大規模言語モデル最適化)の両方を意識したコンテンツ制作が不可欠となっています。
その中でも、特に重要視されているのが「よくある質問(FAQ)」の設置です。

編集部
単にユーザーの疑問に答えるだけではなく、SEOやLLMOの観点から戦略的にFAQを設置することで、コンテンツの評価を高め、検索順位の向上やコンバージョン率の改善につながります。
さらに、専門性の高い情報や、医療・法律などYMYL(Your Money, Your Life)分野のコンテンツでは、専門家による監修者情報を明記することで記事の信頼性を高め、検索エンジンからの評価を上げられます。

編集部
ホームページのコンテンツが検索エンジンやユーザーから高く評価されるためには、その内容が「誰によって書かれ、その情報にどれだけの信頼性があるか」が非常に重要です。

編集部
特に、人々の生活や健康、経済に影響を与える「YMYL(Your Money, Your Life)」分野のコンテンツにおいては、この信頼性がSEO・LLMO対策の鍵となります。
信頼性を高めるための具体的な施策として、著者情報や監修者情報の明確な設置が不可欠です。
SEO対策の基本的なやり方や上位表示させるコツについて知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。
【関連記事】【初心者向け】上位表示させるSEO対策のやり方!具体例や注意点も解説
改修の目的②:コンバージョン(CV)数を増やしたい
ホームページに訪れたユーザーを見込み客や顧客へ変えるためには、次の行動を促す「導線」を見直すことが大切です。
例えば、「お問い合わせ」や「資料請求」といったCTA(Call to Action)ボタンは、以下によってクリック率が大きく変わります。
- 設置場所
- デザイン
- 文言 など
ファーストビュー内や記事の末尾だけではなく、サイドバーなど、ユーザーが行動を起こしやすい場所に最適なCTAを設置しましょう。
また、EFO(Entry Form Optimization)の観点から、お問い合わせフォームの最適化も必要です。
入力項目が多すぎたり、入力方法が複雑だったりすると、ユーザーは途中で離脱してしまいます。
CV率(CVR)を向上させたい場合はフォームの入力項目を必要最低限に絞り込み、入力補助機能も付けましょう。

編集部
ホームページを訪れたユーザーを問い合わせや資料請求といった具体的なアクションへと導くCTAは、コンバージョン獲得において最も重要な要素の1つです。
CTAの設計は、その設置場所や文言もさることながら、「ユーザーの目に留まりやすいデザイン」も大切になってきます。
CVRの基礎知識や改善方法について知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。
【関連記事】 広告運用等で重要なCVRとは?計算式や平均値を紹介!弊社の改善方法も解説
改修の目的③:デザインを刷新したい
デザインの改修は企業のブランドイメージを再構築するうえで重要ですが、単に「おしゃれ」なデザインにするだけでは十分ではありません。
ホームページ全体で以下をはじめとしたデザインテイストを統一することで、プロフェッショナルかつ信頼性の高い印象を与えられます。
- 色
- フォント
- 写真のトーン など
また、顧客ターゲットが若年層なのか、ビジネス層なのかによっても、最適なデザインテイストは異なります。
ターゲットの好みに合わせたデザインでユーザーの共感を引き出し、ブランドへの愛着を高めましょう。

編集部
小さな画面でコンテンツを閲覧するスマホユーザーは、一目で情報を理解できることを求めています。
ユーザーの離脱を招くことがないよう、スマホサイトはPCサイトの構成を流用したり、テキストを羅列したりするデザインは避けましょう。
改修の目的④:使いにくさを改善したい(UI/UXの向上)
ユーザーがストレスなくホームページを利用できるかどうかも、成果を左右する重要な要素です。
今やホームページ閲覧のほとんどがスマートフォンからである分、「テキストが小さすぎる」「行間が狭すぎる」といった状態は、ユーザーに多大なストレスを与えます。
せっかく訪問したユーザーを離脱させないためにも、見やすい・読みやすいデザインへの改修が必要です。

編集部
弊社のホームページ制作ではデザイン要素をまとめた独自のパーツリストを作成し、デザインテイストを統一しています。
ブランドイメージを確立させるとともに、ユーザーが信頼感を覚えるきっかけの1つになっています。
また、ホームページの表示速度が遅いと、ユーザーはイライラしてサイトを閉じてしまいます。
離脱率を低下させるうえでは、画像サイズの最適化や不要なコードの削除など表示速度を改善する改修も必須です。

編集部
ページの表示速度は、ホームページのUI/UX(※)に大きく影響します。
※UI:ユーザーが直接触れるボタンやレイアウト、UX:使いやすさなどサービスや商品から得る体験

編集部
ページの表示速度が遅いとユーザーはストレスを感じ、ホームページから離脱する可能性が高まります。
離脱を防ぐためには画像の遅延読み込み(Lazy Load)や、軽量な画像フォーマット(WebP)の活用が不可欠です。

編集部
表示速度の高速化は快適な閲覧体験の提供につながり、結果としてユーザーの離脱率低下も実現できます。
改修の目的⑤:運用の効率を上げたい
ホームページでは、日々の更新作業を効率化するための改修も大切です。
例えば、専門知識がなくても簡単にコンテンツを更新できるCMSを導入することで、運用コストを大幅に削減できます。
広告タグやアクセス解析タグなどを一元管理できるGTM(Google Tag Manager)も活用できれば、マーケティング施策を迅速に展開しやすくなります。

編集部
ホームページ運用において、アクセス解析や広告効果測定は不可欠です。
しかし、以下をはじめとした複数の計測タグを個別に管理するのは手間がかかり、ミスが発生するリスクもあります。
- Googleアナリティクス4(GA4)
- Googleサーチコンソール
- ヒートマップツール
- 各種広告タグ など
そこで推奨されるのが、GTMの設置です。
GTMを導入すれば、複数の計測タグを一元管理でき、タグの追加・変更・削除も専門知識なしで容易に可能です。
ホームページの運用効率が大幅に向上し、迅速なデータ分析と改善ができるようになります。
ホームページ改修にかかる費用

ここではホームページ改修にかかる費用について、以下の2つを解説します。
- 費用相場
- 会計処理での勘定科目
それぞれ詳しく見ていきましょう。
費用相場
ホームページ改修の費用は、下表のように対応内容によって大きく変動します。
|
対応内容の例 |
費用相場 |
|
テキスト・画像修正 |
数千円~3万円程度 |
|
ページの追加・デザイン修正 |
数万円~20十万円程度 |
|
フォームの最適化・CMS導入 |
10万円~30万円程度 |
全体を通してリニューアルよりも費用を抑えて実施できるのが、改修の大きなメリットとなっています。
会計処理での勘定科目
ホームページの改修費用は、実施した内容によって勘定科目が異なります。
|
改修内容 |
会計処理 |
|
システム・プログラムの大幅な変更 |
資産計上(ソフトウェアなど) |
|
コンテンツの増強や軽微なデザイン修正 |
経費計上(広告宣伝費、修繕費など) |
会計処理に関する詳しい方法は、税理士に必ず相談しましょう。
まとめ:ホームページ改修のターゲットはコンテンツやデザイン

ホームページの「改修」か「リニューアル」か、という問いへの答えは、あなたのビジネスの現状と目的に応じて変わります。
「アクセス数が伸びない」「お問い合わせが少ない」といった具体的な課題が見えているなら、まずはリニューアルではなく、「データに基づいた改修」を検討してみるのがおすすめです。
部分的な改修でも適切な改善を施せば、費用対効果は最大限に高まります。
弊社ではホームページ制作の専門家が、お客様の課題を解決します!
お客様の課題をヒアリングし、データに基づいたホームページ改修・制作を強みとしているので、現状のホームページに課題を感じている経営者様やWeb担当者様は、ぜひ一度お問い合わせください。
「デザインはきれいなのに成果が出ない…」
その原因は、設計段階の見落としにあります。
ただ作るだけでは集客や採用には結びつきません。
成功するサイトに共通する設計プロセスを凝縮した
▶︎
勝てるホームページの型
をぜひご覧ください。

社長の一筆入魂
当社のデータによると、クライアントのコーポレートサイトのリニューアルサイクルは約6年。
そのスパンは年々短くなっています。
これだけ激動の時代において、6年前のビジネスモデルは簡単に陳腐化してしまいますもんね。
できればコンテンツの増強や改修費用に予算を充てた方が良いのですが、ビジネスモデル自体が変わったり、現在のサイト構造自体に課題がある場合はリニューアルをおすすめします。
「改修かリニューアルか」迷ったときは、ぜひ一度ベイスまでご相談ください!

【関連記事】【厳選】三重県のホームページ制作会社7選!サービス範囲・強み・料金も
【関連記事】コーポレートサイトをリニューアルすべきタイミングとは?進め方や事例も
【関連記事】【シーン別】ホームページの制作・運用でやってはいけないこと9選!解決策や事例も解説
ホームページ制作はいい業者との
出会いが8割です
実績数
解析力
伝達力
を兼ね備えた当社に是非一度ご相談ください

まずは御社の商材のファンになることから始めたいので、お問い合わせいただき御社のことを教えてください。
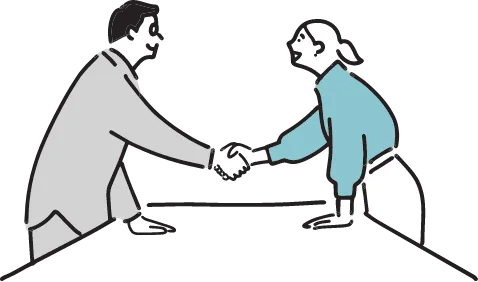
さぁ、ご一緒に
はじめましょう。
具体的なご依頼だけでなく、売り方や集客に関することなど現状の課題についても気軽にご相談ください。